PLAY! MUSEUMで開催中の「どうぶつかいぎ展」(2022年2月5日−4月10日)は、ドイツの詩人・作家、エーリヒ・ケストナーの絵本『動物会議』がテーマです。ドイツ文学の研究者である西尾宇広さんに、展覧会のこと、ケストナーのこと、たくさん聞きました。
「①現代版「どうぶつかいぎ」と 絵本『動物会議』、その違いとは?」はこちら
取材・執筆:永岡 綾
なぜ『動物会議』は時代を越えるのか
— 平和をたたえる物語は数あれど、時代を越えるものと越えないものとがあります。絵本『動物会議』が今も読み継がれるのは、なぜでしょう?
西尾 一つには、ケストナー自身が意図してこの物語を抽象的で普遍的な次元にもっていこうとした、というところがあると思います。
人間の理性に信頼を置く「啓蒙主義」の後継者を自任していたケストナーは、どこかに「正しい見方」が存在していて、それを教えるのが風刺でありユーモアである、と考えていました。
単なるリアリズムでは、本当の現実を見せることにはならない。むしろ、現実とはズレのあるものを見せることで、目の前の現実がいかにおかしいかに気づけるのだ、というわけです。
動物という象徴的な存在を主人公にしたのも、動物ビルがどこにあるかを明示しなかったのも、あえて誇張しつつ単純化して、ユートピア的な世界を描こうとしたのだと思います。


— 確かに! 会議の場所にはまったくふれられていませんね。他方、ケストナーがこの物語を書いた当時の世界情勢が、かなり色濃く反映されてもいます。あのとき、冷戦のいがみあいから、多くの国際会議が実際に行きづまっていたのですよね。
西尾 その通りです。少なくともこれが書かれた当時の読者にとっては、さまざまな点で非常にタイムリーな物語でもあったわけですね。
このことについて、わたし自身は、「本当の普遍性は、徹底的に時代的であるからこそ得られるものだ」と考えています。
そう考えるようになったヒントはいくつかあるんですが、例えば20世紀初頭のオーストリアで活躍したカール・クラウスという批評家が、「素材に生きるものは、素材を前にして死ぬ。言葉のうちに生きるものは、言葉と共に生きる」という言葉を残しています。
当たり前といえば当たり前の話ですが、今ホットな題材だけを追いかけて書かれたものは、その流行が過ぎ去ってしまえばすぐに読まれなくなってしまう、ということです。
でもクラウス自身はといえば、今のわたしたちがちょっと読んだだけではわからないような、当時の社会における時事的な話題を好んで取り上げて風刺的な批評を書きました。そうする中で、「言葉と共に生きる」こと、つまり、時代が変わっても通用するような普遍的な言葉のあり方を追求したのです。
要するに、目下注目を集めている時事的な出来事をただ表面的に取り上げるのではなく、それを徹底的に突き詰めて考え抜くことで、物事の本質的な部分が見えてくる。そこを的確に捉えて書かれた言葉というのは、時代を越えて読み継がれていくのだろうと思います。
後世に残すことを期待するあまり、はじめから作者が実際に生きている時代の具体的な文脈を抑制して書かれたものは、かえって空疎な内容になってしまって残らない。
反対に、徹底してその時代を見つめ抜いて書かれたものは、本質的なところでほかの時代とも通じるところがあり、新しい世代の読者にも読み継がれていく……ということなのではないでしょうか。
さきほどの話と合わせると、一方で抽象度を上げて普遍性を高めつつ、その根っこの部分ではケストナー自身が同時代の具体的な問題を直視している、という構図があって、その問題が未だに解決されていないからこそ、『動物会議』は今もリアリティを保っているのだと思います。
本当は、この作品がリアリティを失って、もう読まれなくなった世界こそが、ケストナーの目指していたものなのでしょうけれど。

ユーモアが人を謙虚にする
— さきほど「ユーモア」という言葉がでましたが、ケストナーのユーモアの感覚って、かわいらしいところもありつつ、ものすごくクールですよね。
西尾 ケストナー自身、笑いとユーモアについてはたくさん書き残しています。
例えば、『ガリバー旅行記』を例にとって、こんな話をしています。ガリバーは巨人の国では小人扱いされ、小人の国では巨人扱いされます。しかし、彼の身長は変わっていない。
ガリバーが二つの国で学んだのは、どこに視点を置くかによって自分の身長が変わるということだ、と。
つまり、地球がいかに小さい星か、長い歴史がいかに一瞬であるか、たいそうな存在だと思っている自分がいかにちっぽけな存在か……そういうことを教えてくれるのがユーモアであり、それが物事を見るための正しい位置であり、正しい視点こそが人を謙虚にする、といっているんですね。
目の前の現実をただ笑っているだけでは、本質的な解決にはつながりません。自分自身は現実の外部にいて、優位な立場に立っているにすぎないからです。
そうやって優位なつもりで笑っている自分自身を笑える、というところまでいって初めて、ケストナーのいう「正しい視点」に立てたことになるのだろうと思います。「自分で自分を笑う視点」ということですね。
— 寄稿文「人間らしい動物たちのリアリティ」では、現実を眺める「距離感」について書かれていますね。われわれは現実を眺める距離が近すぎる、と。
西尾 今、社会のあちこちで分断が進んでいるといわれています。
自分が絶対に正しいと思っている人たちは、相手は絶対に間違っていると思っていて、ひたすら対立が深まっていく。この傾向は、日本のみならず、欧米でも強まっています。
たぶんその背景には、自分で自分を笑う視点をもてていない人が多い、という事情もあるのではないでしょうか。自分が正しいと思い込んでいることが、ほかの視点から見たらちゃんちゃらおかしいことかもしれない。
そういう視点をお互いにちゃんともてていれば、相手との話し方も変わってきますし、そもそも激しい喧嘩にはならないと思うんです。
ところが、ここ数年、日々の生活の中でそういう視点をもちづらくなっているように感じます。
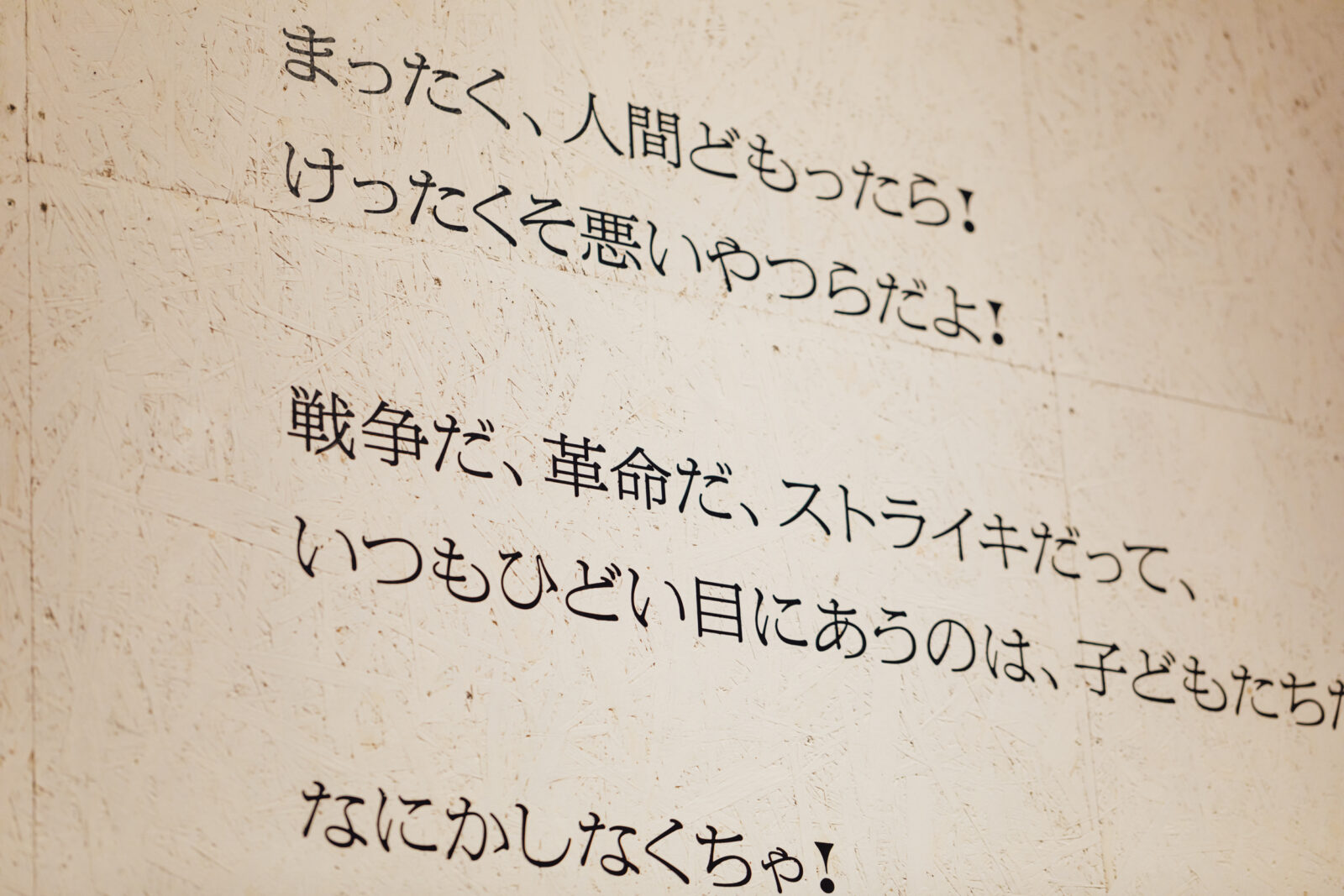
— なぜだかよくわからないけれど息苦しい、と感じている人は少なくないと思います。
西尾 それは、視野が狭いとか経験が足りないとか、そういった個人の問題ではなくて、結局のところ社会の問題なのだと思います。
笑うためには、時間的なこと、経済的なことも含めて、余裕が不可欠。それなのに、今、多くの人がそれをもてていない状況があります。
— 「どうぶつかいぎ展」が、ユーモアの感覚にふれる一つのきっかけになったらうれしいです。
西尾 PLAY! MUSEUMのような日常とはちょっと違う空間で、普段とは別の視点で物事を眺めてみるのは、とても大事なことだと思います。クスッと笑えるところがあったなら、ぜひ、そうやって笑っている自分を笑う視点を探してみてほしいですね。


③「ケストナーさん、今、何を書きたいですか?」につづきます!

西尾宇広(にしお・たかひろ)さん
1985年、愛知県生まれ。慶應義塾大学准教授。専門は近代ドイツ文学。卒業論文でケストナーに取り組んで以降、「公共圏」というキーワードのもと、文学が社会のなかで果たす役割について歴史的な視野で考えている。主な仕事に、『ハインリッヒ・フォン・クライスト――「政治的なるもの」をめぐる文学』(共著、インスクリプト、2020年)など。
永岡 綾(ながおか・あや)
編集者・製本家。「どうぶつかいぎ展」企画メンバーの一人。編書に『アーノルド・ローベルの全仕事』『かえるの哲学』『ちいさなぬくもり 66のおはなし』『柚木沙弥郎 Tomorrow』(ブルーシープ)など。著書に『本をつくる』(河出書房新社)、『週末でつくる紙文具』(グラフィック社)など。










