Netflixで配信中の長編アニメーション『ONI ~ 神々山のおなり』の世界観を味わうことができる展覧会、トンコハウス・堤大介の「ONI展」。この作品の監督を務めた堤大介さんに、展覧会と『ONI』の制作秘話について伺いました。
取材・執筆:内山さつき
会場撮影:田附勝
ポートレート撮影:高見知香
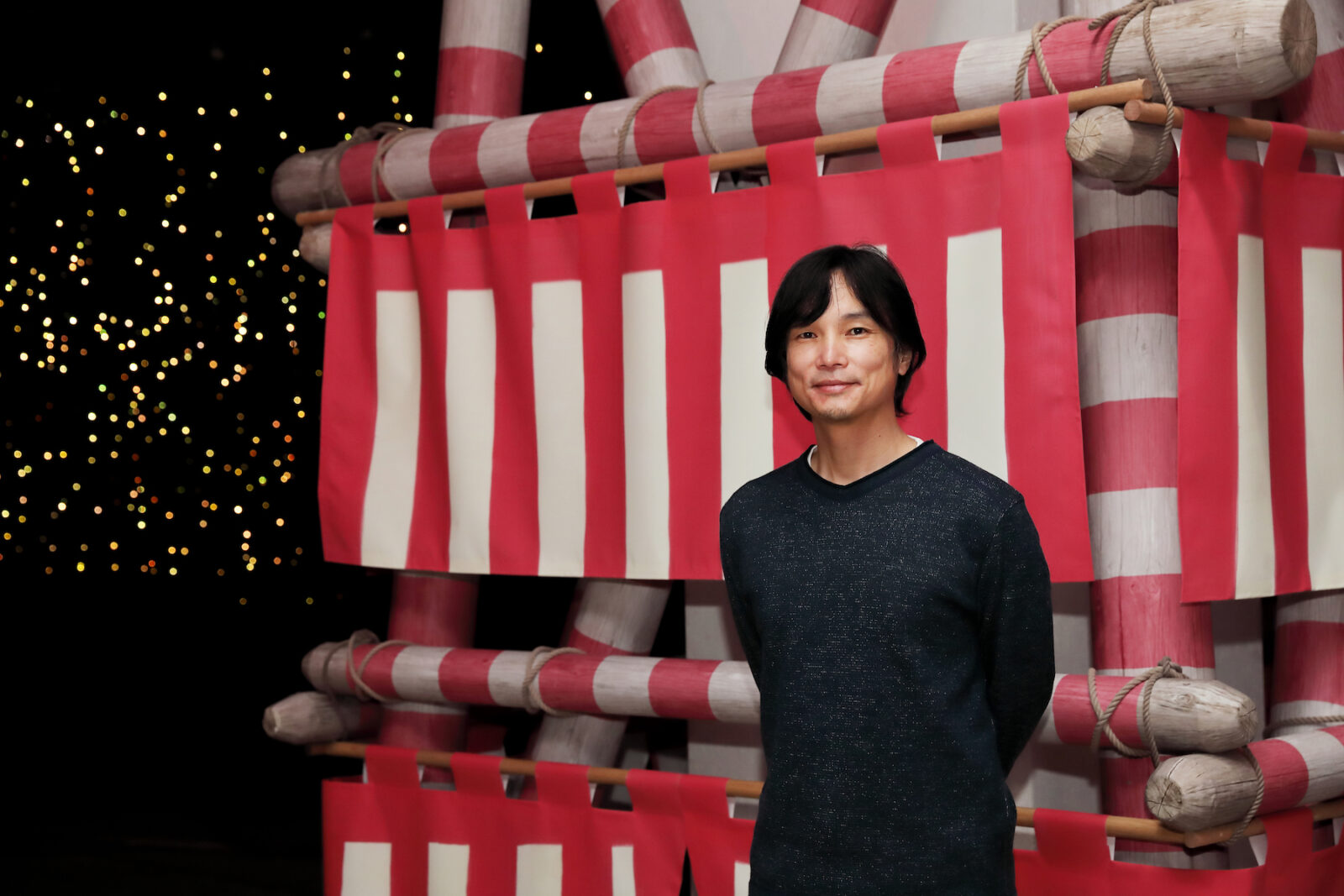
―展覧会をご覧になった感想を聞かせてください。
堤 アニメーション作品の展覧会というと、通常はメイキングの原画展が多いと思うのですが、今回はPLAY! MUSEUMの大きなスペースを使って、映像を贅沢に見せたらどうなるのかを、菱川さんはじめとするプロデュースチームが見事につくり上げてくれました。自分がつくった作品を、全く新しい視点で楽しめました。
―『ONI』は2022年10月21日から配信が開始されましたが、展覧会と作品の制作はほぼ同時進行だったのではないでしょうか。
堤 展覧会の企画は一年ぐらい前に決まっていたのですが、『ONI』が完成して納品できたのは、実は配信の1週間前というギリギリの進行でした。なので、展覧会制作チームにもなかなか完成版をお見せできずにいたんです。
プロデュースチームから展覧会の構想を聞いたとき、僕が予想していたものとは全く違っていたので、自分が想像できないところに連れて行ってくれるのではないかというワクワク感がありました。それで展覧会の方は多くの部分をお任せすることにして。その分、メイキングをまとめた公式アートブック『ONIのすべて 〜トンコハウスと堤大介、旅の途中〜』は頑張りました。インタビューやメイキングの画像もふんだんに用意して、ボリュームたっぷりの図録になっていますよ。

公式アートブック『ONIのすべて 〜トンコハウスと堤大介、旅の途中〜』 
公式アートブック『ONIのすべて 〜トンコハウスと堤大介、旅の途中〜』 
公式アートブック『ONIのすべて 〜トンコハウスと堤大介、旅の途中〜』 
公式アートブック『ONIのすべて 〜トンコハウスと堤大介、旅の途中〜』 
公式アートブック『ONIのすべて 〜トンコハウスと堤大介、旅の途中〜』 
公式アートブック『ONIのすべて 〜トンコハウスと堤大介、旅の途中〜』
―展覧会の空間デザインの中で惹かれたのは、どんなところですか?
堤 天井から下げられた和紙にアニメーションが投影されているのが素敵でした。空調で揺れていたのが、風に揺れる演出なのかと思ったぐらい自然で。それは家でテレビや端末で観ていたら体験できないことですよね。和紙にはあんなに色鮮やかに映るのかということにも驚きました。
目玉はやっぱり太鼓が置いてあるクライマックスの演出です。真っ暗な中に太鼓が1つ置いてあって、誰でも叩いていい。演出がちゃんと物語とつながっていて、森の精霊「モリノコ」がワーッときらめくのにも感動しました。

「ONI展」会場写真(撮影:田附勝) 
無数の森の精霊「モリノコ」がきらめくインスタレーション
言葉を超えて伝わっていくもの
―『ONI』は、31か国語に翻訳されて配信されているのですね。
堤 はい、先日はウクライナの家族から一つビデオが送られてきて。6歳ぐらいの女の子が、「どんつこつこつこ、わっしょいわっしょい」と言いながら踊っている姿でした。彼らの住む場所は、戦場から少し離れてはいるものの、電気や水が止まることが度々なのだそうです。そんないつ戦争がやってくるか分からないような状況の中でも、その子が楽しそうに踊ってくれる姿を見て本当に嬉しかった。日本語、日本の文化を知らなくても、世界の子どもたちがお祭りの掛け声を楽しんでくれていることに、胸打たれました。
―『ONI』ではみんなが同じ生きもので、優しい人たちもいて、同じように暮らしているということを象徴的に描いていますね。
堤 まさに今、認識しなければいけないことですよね。自分が理解できないものを排除しようとする心は誰もが持っている。一部の悪い人たちが差別するのではなく、恐怖から排他的になるのは誰にも起こりうること。『ONI』は敵味方という構造ではなく、自分の中の闇にどう打ち勝つかという物語にしたかった。

「ONI展」会場写真(撮影:田附勝) 
「ONI展」会場写真(撮影:田附勝)
堤 僕は日本古来の考え方はすごく面白いなと思っています。日本の「鬼」は、必ずしも悪者としてだけではない一面もある。例えば「鬼瓦」は魔除けだし、歴史上は罪人になって「鬼」として扱われたけれど、今では神様として祀られている人物もいます。日本では神様や妖怪、鬼などの概念が曖昧です。悪いものは排除しようとする西洋的な考え方とは違って、「光と闇」もある意味曖昧であるのが、日本の文化の特徴的なところですね。
―「光と闇」という言葉がありましたが、この作品は光の表現がとても美しいですね。昼、夜だけでなく夕方の柔らかい光やおぼろげな光など、様々な光が描かれているのが印象的です。
堤 僕は学生のときは貧乏であまり旅行はできなかったのですが、社会人になってからは世界中を旅しました。光はその土地の気候、空気の濃度、湿気によって見え方が違います。光が強い、弱いということもあるのですが、人が体験する光は、光源と自分までの間の空気や湿気、建物や自然物などに影響を受けるわけですよね。だから、自分の目に入ってくる空気感のすべてなのかなと思います。
旅をした中で、日本は特に印象的でした。作品の中でも、日本ならではの色彩を意識しています。CGで森の湿気が感じられるように作るのはとても難しい。CGだからと言って、決まった数値を入れたらポンッと出てくるわけではないので、最終的には自分の感覚の判断になり、絵を描くのとそれほど変わらないのです。この作品を日本のアニメーションスタジオと連携して作ることにこだわったのは、やはり日本の気候、天候、光を分かっている人たちでないとこの空気感は出せないと感じたからです。

スタッフみんなで作り上げた物語
―メインキャラクターの一人でもある「なりどん」が言葉を持たないというのも面白かったのですが、それは早い段階から決めていたのですか?
堤 「なりどん」がしゃべらないのは、僕の中では最初からイメージがありました。でも父親と娘の関係を描く物語で、父親がしゃべらないでどうするのかという指摘は、初期からトンコハウス内でもありましたし、Netflixからも受けました。それは反対ではなく、作り手をサポートしたいからこその指摘だったので、なぜそうでなければいけないのか、きちんと説明する必要がありました。初めは感覚的なものでしたが、物語を作りながら、おしゃべりな娘と話さない父親という関係はやはり面白いと思いました。そこはアニメーションなので、言葉を持たない「なりどん」がどういう表情や仕草をしたら観る人に伝わるのかというのも挑戦だと思ったのです。
共にトンコハウスを立ち上げたロバートが言っていたことも参考になりました。ロバートには娘がいて、「自分も娘の考えていることを果たしてどこまで理解しているか、父親として不安はある。だんだん『なりどん』の気持ちがわかってきたよ」と。そういう風に考えると、「なりどん」みたいなお父さんは世の中に結構いるんじゃないかと。

―口下手なお父さんは一層「なりどん」に共感するかもしれないですね。「なりどん」の仕草や表情は愛情に満ちていて、印象に残るキャラクターです。
堤 3話の最後で、「おなり」が「なんで言ってくれなかったの」と、「なりどん」を責める場面があります。父親の方も説明できないもどかしさがあるんですよ。でも、大切なのはどう説明するかではなく、「なりどん」が注いだ溢れるような愛情を、「おなり」がどう受け止めるかなので、「なりどん」が話さないという設定にしたのは結果的に良かったと思っています。
―トンコハウスでは、ストーリーもスタッフの中でディスカッションしながら決めるというのが興味深かったのですが、物語を着地させる部分で難しかったことはありますか?
堤 物語の結末は、脚本の岡田麿里さんに入ってもらう前から僕の中にあったのですが、それを「どう見せるか」が難しかったです。どう終わらせたら観る人に納得してもらえるのか、「おなり」が感情的に行きつくべきところにきちんと着地できるのか。岡田さんとのやり取りはもちろん、ストーリーボードの過程でも何度も練り直しました。ストーリーボードとは、アニメーションを作る上での絵の脚本のようなものですが、そのスタッフの意見もとにかく聞きました。もちろん最終的には責任を持って僕が決めなくてはいけませんが、みんなで一生懸命考えました。スタッフの熱量がそれだけ高かったのは、みんなが「これは自分の物語だ」と思っていてくれたからだと思います。

『ONI ~ 神々山のおなり』場面写真© 2022 Tonko House Inc. 
『ONI ~ 神々山のおなり』場面写真© 2022 Tonko House Inc. 
『ONI ~ 神々山のおなり』場面写真© 2022 Tonko House Inc.
―この展示を見に来るお客さんには、特にどういうところに注目してもらいたいですか?
堤 Netflixで『ONI』を観てくれた方も観ていない方も、新しいものを見るつもりで来ていただけたら。作品を知っている人たちは、もちろんまた違った楽しみ方ができますが、映像の投影やメイキングの過程、太鼓の演出などとにかく素敵な空間をまずは体験してもらえたらと思います。
―これからどんなことをやってみたいですか?
堤 とにかく作品を作り続けていかないといけないというのはありますね。作ることで見えてくるものがあります。何より、日本を題材に作品がつくれたことが幸せでした。今回やりとりをしていたアメリカ側のNetflix本社が、この作品をつくろうと言ってくれたこと自体が奇跡だったと思います。
次の作品も可能であれば、日本を舞台にしたいという気持ちを持っています。日本の外にいる日本人の僕だからこそ伝えられることがあるのかなと思うので、そういう作品をまたつくってみたいと思いながら、温めているところです。
『ONI ~ 神々山のおなり』作品視聴はこちらから

堤大介(Daisuke “Dice” Tsutsumi/つつみ・だいすけ)
東京都出身。スクール・オブ・ビジュアル・アーツ卒業。ルーカス・ラーニング、ブルー・スカイ・スタジオなどで 『アイスエイジ』や『ロボッツ』などのコンセプトアートを担当。2007年ピクサーに招聘されアートディレクターとして 『トイ・ストーリー3』や『モンスターズ・ユニバーシティ』などを手がける。2014年7月ピクサーを去りトンコハウスを設立。初監督作品『ダム・キーパー』は2015年米アカデミー賞短編アニメーション賞にノミネート。2021年には日本人として初めて米アニー賞のジューン・フォレイ賞を受賞。一冊のスケッチブックに71人の著名なアーティストが一枚ずつ絵を描き、手渡しで世界中を巡るというプロジェクト『スケッチトラベル』の発案者でもある。










-456x640.jpg)
